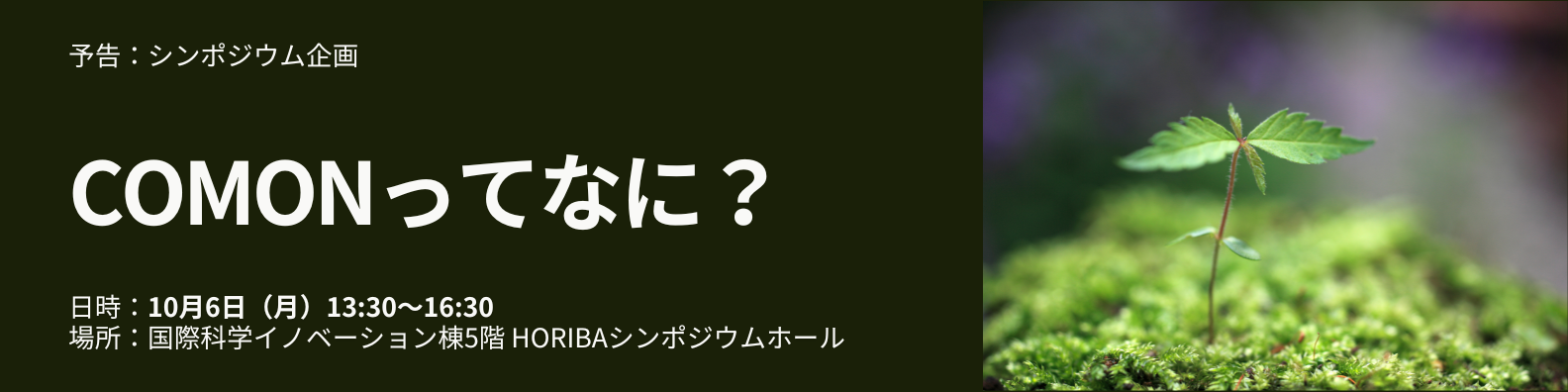From metrics to dialogue-based culture ― COMON is Kyoto University’s way of co-creating a new COMMON.
序列化から、対話による価値共創へ ― COMONは、対話を通して京都大学独自の学術文化を創造していく共創の場です。
“研究者になりたい”という未来の若者に、
大学は何が残せるのだろうか?
研究費やポスト獲得などの過度な競争、分野横断的研究や地域連携研究などの新たな研究の展開に馴染みにくい定量評価、基盤経費など安定した資金の削減、専門的な技術者・事務員の不足、業務過多による研究環境の悪化、それに伴う時間的・精神的余裕の欠失が、真に重要な学術課題に直結する研究、地域課題の解決、国際連携研究への研究者の挑戦を阻んでいるのみならず、さらなる国外への人材流出や大学院生の減少を招いている
日本学術会議若手アカデミー
「見解 2040 年の科学・学術と社会を見据えて いま取り組むべき 10 の課題 」2023年9月より
いまの京都大学に求められているのは
多様性
学術領域を先導する研究も、時間をかけて熟成する研究や市民とともに社会課題に取り組む研究も、多様な知の共存と共鳴が新たな知を生む源であることを理解し、その多様性を次世代に継承すべく育むこと
透明性と説明責任
研究者同士が熟議により目指すべき将来像を定め、そのために必要とされる、研究時間の確保や人材育成策などを含む計画を自ら策定し、それを開示し透明性を確保し、将来世代への責任を果たしていくこと
対話による共創
若手とシニア、大学本部と部局など学内での対話や、地域社会や学生との対話の機会を増やし、学び合いながら学術の源であるコモン(共有地、公共財)を社会とともに育てること
対話により、京大独自の学術文化をともに創造していく
その共創の場が COMON です
なぜ COMON が必要なのか?
研究評価のあり方が、いま世界中で見直されています。高インパクトジャーナル掲載論文や被引用数の多い論文の数だけでは、長期間の熟成を要する研究や社会の課題に向き合う研究の価値を把握することはできません。
京都大学は、自由の学風と研究の多様性を次世代に継承するために、既存の評価方法に依存しない、新たな共通基盤を必要としています。
COMONは、一律の指標による序列化ではなく、研究組織ごとのビジョンに基づき、
「自ら評価のものさしを作り、対話と共創によって未来を描く」ための仕組みです。
COMON とは
京都大学がこれまで大事にしてきた研究の価値を5つの軸で表し、その頭文字からCOMON<コモン>と名付けました。
コモン(Commons)は「共有地、公共財」を意味します。
大学は社会の公共財として、学術的価値を生み出し、社会に生きる人々との多様なつながりにより社会に貢献することが求められます。COMONという5つの特性で示される学術的な価値(創造的先進性、波及性、汲集性、伏流性、積層性)は、本学が培ってきた研究の多様性を象徴しています。

これらの特性は、従来から京都大学が培ってきた高い専門性や卓越した研究成果を基盤としつつ、その多様性を広く共有し、次世代に継承していくためのものです。学術の価値は一つの尺度で測りきれるものではなく、あらゆる研究の営みが持つ固有の意義を尊重し、社会とともにその豊かさを育てていく姿勢が、 COMONの根幹にあります。
この5つの特性からなる多様性を共有すべき価値として中心に据え、次世代に継承していくためには、構成員それぞれが責任を持って対話と熟議を重ね、不具合を調整しながら協業し、コミュニティとして持続的なCOMONの再生に取り組むことが必要です。
そして研究の果実を研究室や大学や学術界に留めるのではなく、「Common Good(共通善)」への貢献を念頭に、より広く地球的な視野で積極的に社会的責任を果たしていくことが求められます。
COMONは、これまでの研究の営みによって築かれてきた多様な成果を土台に、それらを起点として、より広い学術的価値やつながりを見つめ直すための新しい視座を提供します。 「地球社会の調和ある共存に貢献する」という本学の基本理念に基づき、本学の研究特性を表す5軸をもとに学内で対話を促進し、京大独自の学術文化を創造していくための共通基盤です。
互いのことを知らずに協働はできません。大学として大事にする価値が5軸の多様性にあることを大学本部が初めて明らかにしたことで、対話の糸口ができました。COMONという共通基盤を通して、大学本部は研究組織を、研究組織執行部はその構成員や学生の多様な声を、あるいは大学本部や隣の研究組織をより深く知ることができます。さらに、この共通基盤が公開されることで、大学は社会により一層開かれた公共財としての価値を発揮することができます。それぞれの特性を尊重しながら対話し、理解し合い、切磋琢磨することにより、将来の研究者を育む、新しい京大発の学術文化が生まれます。
京都大学は、世界的な研究評価改革の潮流の中で
議論と実践を積み重ねてきました
研究評価のあり方は、世界中の大学・研究機関で見直されています。
どうしたら、分野の多様性を損なわず、研究者が主体的に評価に携わることができるのか?──
この問いに、京都大学もまた長年取り組んできました。
COMONは、国内外の議論や実践をもとに、京都大学が独自に設計した新たな評価の共通基盤です。
京都大学における実践(国内)
国内では、若手支援や分野特性に即した新たな評価のあり方を模索してきました。
以下はその具体的な実践の一部です。
- L-INSIGHT: 若手メンター制度を軸とした「支援的評価」を導入
- 研究評価に関する課題のマッピングを人文・社会科学系URAネットワークのURA有志で実施:人文・社会科学系研究の評価に関する地図Ver.1
- IRセミナーシリーズ第5回 京都大学で『責任ある研究評価』を考える(2023年12月8日)
責任ある研究評価(Responsible Research Assessment)をテーマに、学内での対話を促進 - 多様性と持続可能性: 責任ある研究評価と大学改革の課題(2024年10月8日)
評価改革を制度・組織の変革と一体的に議論する場として、全国の実務者・政策担当者・研究者を招いたシンポジウムを開催
「責任ある研究評価」における国際的な議論では、評価対象や方法論の継続的な見直しがされているだけでなく、大学制度・資源配分・人事制度への影響と不可分の課題として取り扱われています。京都大学もこうした視点を共有しながら、評価制度そのものだけでなく、大学制度と学術文化の両面から持続可能な知のあり方を模索しています。
国際連携と潮流の把握
同時に、国際的にも研究評価改革に関する動向を注視し、多くの機関・ネットワークと情報共有を重ねてきました。
- 研究評価におけるジャーナルインパクトファクターの使用制限などを提起した、研究評価に関するサンフランシスコ宣言:DORA
- 研究評価における計量データの利用についての10の留意点を示した研究計量に関するライデン声明
- 研究評価における指標の利用とピアレビューのバランスについてまとめたメトリックタイド報告書
- 研究評価改革を加速するためのコアリション:CoARA
- オランダの公的研究機関および研究資金提供者による学術評価とキャリア報奨の抜本的見直し方針:Room for everyone’s talent
- 研究システムと研究文化の変革を目指す国際連携機関(RoRI)による研究機関インパクトレポート など
研究のエコシステムの持続可能性は、評価のあり方によって大きく左右されます。研究のエコシステムが持続していくためには、研究評価も継続的に更新されて必要があります。
COMONはこうした国内外の知見と実践を踏まえたうえで、京都大学が独自に設計した評価基盤です。
京都大学は、“共通のものさし”で測るのではなく、
未来をともに描く対話の場を選びます。
それが、COMONです。
動き始めた COMON
京都大学では、新しい研究評価システム:COMON の運用を開始するにあたり、制度の意図を共有し、現場の実情に即した対話を重ねながら、準備を進めています。
2025年10月6日には、COMONをテーマとした学内外向けシンポジウムを開催予定です。